令和6年度症例検討会
西多摩リハビリテーション研修会では以下の日程で症例検討会を開催致します。今年度は5年ぶりに対面での開催となります。当会の症例検討会は毎年PT、OT、STの3職種による発表があることが特徴で、今年度もリハ3職種が発表予定です。多摩地域の若手療法士の先生が発表してくださいますので、活発な意見交換およびリハ職交流の場となりますよう、多くの方のご参加をお待ちしております。事前申し込みは不要です。多くの方々の参加をお待ちしております。
抄録はこちらから→ 症例検討会抄録集2024.pdf
症例検討会抄録集2024.pdf
日時:令和7年2月6日(木)18時30分から20時10分
会場:公立福生病院 1階多目的ホール *対面開催となります
発表形式:口述発表(パワーポイント使用)発表7分、質疑5分(予定)
発表演題数:6演題(PT2演題、OT2演題、ST2演題)
参加費:無料
申し込み:事前申込不要(当日、会場で受付を行います)
プログラム
18 時30分 開会挨拶
18 時35分 第1セッション
【演題1】
肺炎後の廃用症候群で既往に全身性エリテマトーデスを呈した症例
~自宅での入浴動作獲得を目指して~
羽村三慶病院 作業療法士 野本亜美
【演題2】
独自の方法でADLを確立していた対象者に対し,自宅環境を再現することでADLへ反映できた症例
大久野病院 作業療法士 榎戸愛菜
【演題3】
重度の感覚性失語症者に対するコミュニケーション代償手段の一考
~シミュレーションを通した家族指導と練習~
羽村三慶病院 言語聴覚士 岡部浩也
19時15分 休憩
19時25分 第2セッション
【演題4】
身寄りがない失語症者 今後の生活が安心して安全に送れるように
~STに求められること・出来ること~
青梅三慶病院 言語聴覚士 水葉貴之
【演題5】
人工股関節周囲骨折術後に生じた脚長差に対して補高をして歩行獲得・自宅退院した症例~立脚期荷重応答に着目して~
高木病院 理学療法士 河邊尚之
【演題6】
脊柱管狭窄症を伴う腰椎変性すべり症において脊柱管狭窄症のみ手術適応となった1症例 ∼痛みを調整しながら体幹アップライトに着目して∼
高木病院 理学療法士 原島梨那
20 時05分 閉会挨拶
【問い合わせ先】
西多摩リハビリテーション研修会事務局
(羽村三慶病院リハビリテーション科)
佐藤、川村
℡:042-570-1130
E-mail:reha@hamurasankei.or.jp
令和6年度第2回定例講演
日 時:令和7年3月5日(水曜日)
時 間:19時00分から20時30分
場 所:オンライン(ZOOM)
テーマ:糖尿病治療マネジメントの基礎とリハビリテーション現場での注意点
講 師:相澤 郁也 先生(理学療法士)
医療法人社団三咲内科クリニック
第11回日本糖尿病理学療法学会学術大会 広報部長)
チラシはこちらから⇒ Nishitamareha2nd_2024_A42028129.pdf
Nishitamareha2nd_2024_A42028129.pdf
申込みはこちらから⇒ 申込みフォーム
申込みフォーム
令和6年度総会 第1回定例講演
盛会のもと終了いたしました
日時:令和6年6月13日(木曜日)
時間
総会 18:00~18:25
第1回定例講演 18:30~20:00
場所:オンライン(ZOOM)
第1回定例講演テーマ
「前庭リハビリテーション入門」~前庭の基礎から実践例まで~」
講師:松村 将司 先生(理学療法士)
杏林大学 保健学部 リハビリテーション学科
第1回定例講演フライヤー⇒ 令和6年度第1回定例講演フライヤー
令和6年度第1回定例講演フライヤー
第1回定例講演 開催報告
~研修後記~
第1回定例講演には杏林大学 保健学部 リハビリテーション学科 で講師としてご活躍されております理学療法士の松村 将司 先生をお招きして「前庭リハビリテーション入門~前庭の基礎から実践例まで~」というテーマでオンラインにてご講演いただきました。当日はオンライン上にて100名を超える方が参加され、大変盛況となりました。
松村先生には前庭リハビリテーション入門として解剖から介入とそのエビデンスまで幅広い内容を大変分かりやすく講義していただきました。目まいを訴える患者様は日常の臨床で接することが多いにもかかわらず、前庭リハビリテーションは私自身にとって知識の乏しい分野でありました。松村先生の講義を通して、患者様の訴えにはきちんとしてエビデンスとリハビリテーションで対応できるということ、高齢者の転倒予防にもつながることを学ぶことができました。また、松村先生からはリハビリテーション専門職として日々研鑽するうえでの学びの場の提案もしていただき、大変有意義な講演会となりました。
(文責 大久野病院 作業療法士 木住野善章)
令和6年度 総会
終了いたしました。会員のみなさまご協力ありがとうございました。
日時:令和5年6月15日(木曜日)
時間:18:00~18:25
場所:オンライン(ZOOM)
令和6年度 総会開催報告
今年度も昨年に引き続き、オンラインでの総会開催となりました。会員の皆様のご協力のもと、多数のご参加と委任状により総会成立することができました。有難う御座いました。議案は前年度の活動報告と会計報告、今年度の活動計画、新旧役員の交代について執り行われ、すべての議案が賛成多数により可決されました。
(文責 大久野病院 作業療法士 木住野善章)
令和6年度 縦断的症例報告会
盛会のもと終了いたしました
~同一患者様の急性期・回復期・生活期における症例報告~
今回、各病期おけるリハビリテーションと施設間連携をテーマに症例報告会を行うこととなりました。同一患者様の急性期に、回復期に、生活期におけるリハビリテーションや施設間連携等について、各病期を担当した療法士の先生よりご報告して頂きます。西多摩地域における各病期の役割やリハビリテーションの内容、施設間連携などの理解が深まる報告会です。是非、ご参加ください。
日 時 令和6年10月24日(木曜日)
時 間 18時30分から20時00分
場 所 オンライン(ZOOM)
案内用チラシ⇒ 案内用チラシ
案内用チラシ
報告者
- 急性期 橘 敦彦 先生 ( 公立福生病院 理学療法士)
- 回復期 奥野美咲 先生(羽村三慶病院 理学療法士)
- 生活期 本橋 利美 先生(介護老人保健施設ユーアイビラ 理学療法士)
- 横須賀 怜 先生(介護老人保健施設ユーアイビラ 理学療法士)
開催報告
縦断的症例報告会では、一症例を通して、各施設の役割を提示していただきながら患者様へのアプローチやリスク管理について講義いただきました。近隣の施設で働くリハビリスタッフが顔を合わせて症例について共有する場となり、西多摩リハビリテーション研修会が発足した当初の形に戻ったような報告会となりました。 今回はオンラインでの講義となり、54名の方に参加頂きました。 今回の報告会を通して、各病期での考え方や症例の捉え方を情報共有することができ、日頃のリハビリテーション経過報告書でどのような情報が重要なのかイメージすることができるようになったかと思います。今回の症例は急性期病院、回復期病院、また他施設の急性期病院を経て、回復期病院、生活期施設へと転帰された方です。 その中で、どの施設も腎不全に対してのリスク管理をして全身状態を評価しながら、トイレ動作獲得、歩行の獲得、ADLの介助量軽減に向けてリハビリを提供していることに驚きました。一症例を通して報告会をする中で、各病期での役割は違うが同じポイントを捉え て、一貫とした目標を合わせながらのリハビリテーションが提供されていたと思います。地域連携によって長期間の間、シームレスにリハビリテーションが提供され、入院後から老人保健施設を退所されるまで充足したリハビリを実施することが出来ていました。ただ、複数回にわたり転院を繰り返されると経緯の時系列を辿ることが困難であったという課題もあがりました。発表者間で活発に質疑 応答も行われ大変有意義な時間となりました。この報告会を通して、さらに情報共有を充実させて患者様、利用者様により良いリハビリを提供していきたいと鼓舞されるようでした。
(文面 公立福生病院 理学療法士 野々村達也)
応募先・問い合わせ先
西多摩リハビリテーション研修会事務局
(羽村三慶病院リハビリテーション科 佐藤 川村)
Tel:042-570-1130
E-mail:reha@hamurasankei.or.jp
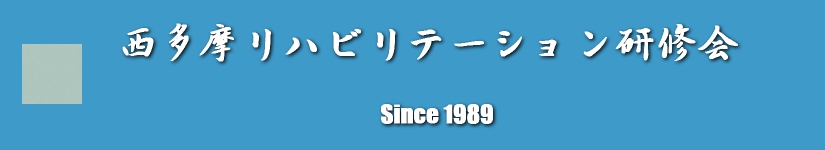
 HOME
HOME